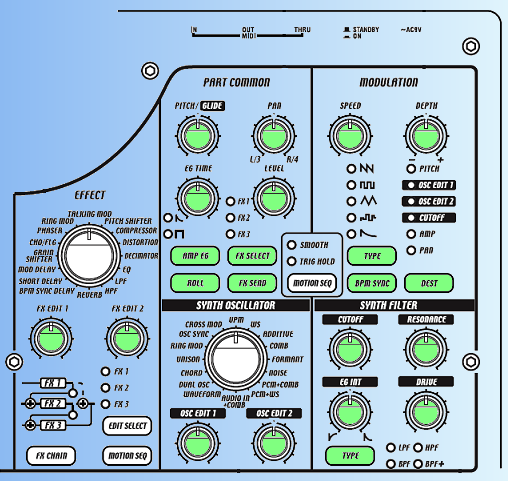
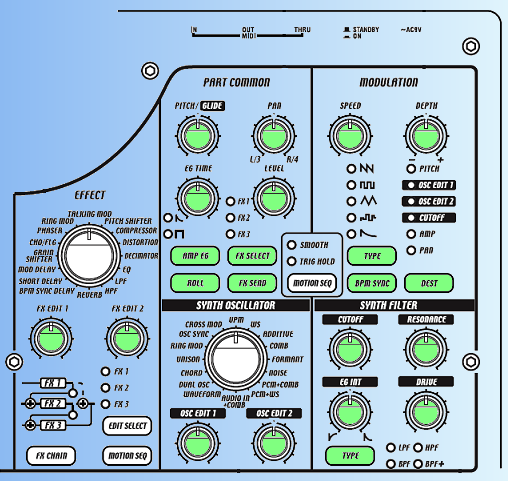
※ 緑色で示したツマミやボタンはモーションシーケンス対応です。
たくさんツマミやボタンがありますが、大きく分けて5つのセクションがあります。
セクション1つ1つ順を追って見ていけば、そんなに複雑ではないことが判ります。
1.エフェクトパラメータ
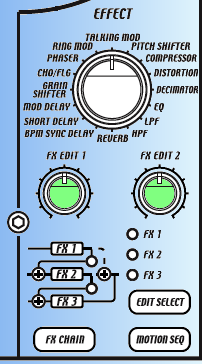 エフェクターは16種類あり、3系統同時使用可能です。
エフェクターは16種類あり、3系統同時使用可能です。
ツマミで種類を選択します。
「FX CHAIN」ボタンで3つのエフェクターの繋げ方が自由に設定出来ます。
例えば、3つ並列に使って3種類を使い分けるとか、
2つは音色加工用に直列に繋ぎ(ディストーション+ディレイとか)、
1つはマスターエフェクトとしてコンプレッサーやEQにする、
またはリバーブで残響効果を出すなどです。
使い方は様々です。いろんな組み合わせが考えられます。
各エフェクトに2つずつパラメータがあり、
それぞれ「FX EDIT」ツマミに割り当てられています。
「EDIT SELECT」ボタンで編集するエフェクト番号
FX1〜3を選択してエディットしていきます。
詳しい解説は「エフェクター」の章で解説します。
2.パートコモンパラメータ
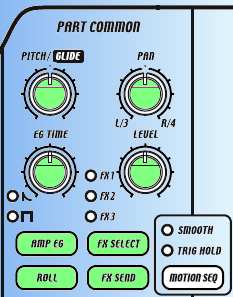 各パート毎に音量(及び音量の時間的変化)、左右の定位、
各パート毎に音量(及び音量の時間的変化)、左右の定位、
ピッチ/グライド(ポルタメント)など、共通パラメータを設定します。
トラックに設定した音を連打する「ROLL」ボタン、
エフェクターのオンオフを決める「FX SEND」ボタン、
どのエフェクトに信号を送るか決める「FX SELECT」ボタンもあります。
※ 「PITCH/GLIDE」ツマミはドラムパートの場合ピッチ、
シンセパートの場合グライド(ポルタメント)の時間設定になります。
※ グライド(ポルタメント)とは
ゲートタイム(鍵盤を押している時間)の長さが、
次の発音のタイミングを越えた場合、トリガーしないで、
次の異なる音程へピッチ変化を滑らかに繋ぐ機能です。
※ ROLL(連打)の仕方はテンポとROLLタイプ、
スイング(シャッフル効果)の設定によって変わります。
3.モジュレーション
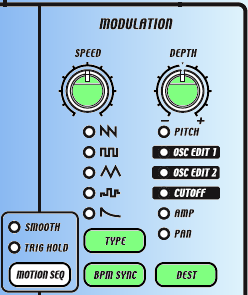 パラメータに揺らぎを与えるModulation(LFO)を設定します。
パラメータに揺らぎを与えるModulation(LFO)を設定します。
揺らし方の種類と揺らしたいパラメータを決め、
揺らすスピードと深さをツマミでコントロールします。
揺らす先が音量ならトレモロ、ピッチならビブラート、
フィルターならワウワウになります。
PANに掛ければ音が左右に動き回ったりします。
シンセサイザーの場合、パルス波の幅にモジュレーションを掛ければ
パルスウィズモジュレーション(PWM)になったり、
VPM(FM)やリングモジュレーション、フォルマントの
パラメータを揺らせば、普通のPCM音源では不可能な音色変化が楽しめます。
※ 「DEPTH」はプラス方向とマイナス方向があり、マイナスにすると
効果が逆再生になります。例えばノコギリは「上から下」だったのが
「下から上」に上がるようになったりします。
4.シンセ・オシレーター
※ シンセパートのみ使用
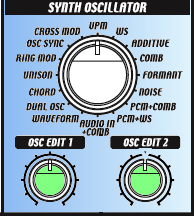
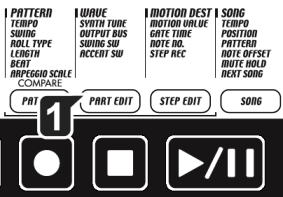
シンセサイザーの音源方式を16個の中から選びます。
それぞれの音源には必ず2つパラメータがあり、「OSC EDIT」ツマミに割り当てられます。
波形の種類を選んだりする場合は「PART EDIT」の「SYNTH TUNE」で設定します。
5.シンセ・フィルター
※ シンセパートのみ使用
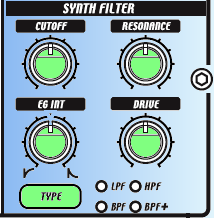 4種類のレゾナンス付きマルチモードフィルターの種類と周波数調整、
4種類のレゾナンス付きマルチモードフィルターの種類と周波数調整、
ドライブ(歪みを与える)回路の歪み具合が設定可能です。
「EG INT」ツマミでフィルタの時間的変化の仕方を変えます。
真ん中が変化なしで、左側は最初ゼロで徐々に開く、
右側は全開から徐々にゼロに向かっていくようになります。
フィルターの詳細はシンセパートエディットの章で詳しく解説します。